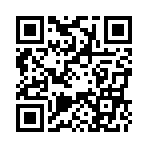2009年08月22日
孫の質問攻め
私には小学校2年生を頭に下は3歳までの4人の孫がいる。その孫に質問攻めにあっている。「これ何、どうしてなの」と見るもの、聞くものなんでも聞いてくる。質問の多いのは一番下で、上にいくにつれて少なくなっていく。自分なりに意味がわかり、納得していくのだろう。
質問の数は少なくなるが、質問のレベルは上がってきて、時にはすぐに答えらずにインターネットや辞書で調べることも増えてくる。しかも説明がうまくできなかったり、要領を得なかったりすると時間がかかる。でも理解した時の「わかった」という満足そうな顔を見ると教え甲斐がある。
ギリシャの物理学者アルキメデスは風呂の中で浮力の原理が頭の中に閃いた瞬間「ユーレカ」と叫んで風呂から飛び出し、裸のまま街を走ったという伝説がある。熟慮に熟慮を重ねた末の「ユーレカ」という嬉しさが溢れていたのだろう。「ユーレカ」とはギリシャ語で「発見した、わかった」という意味である。
私たちにも経験はあるだろう。小さい時は親や先生などに何でも質問してきて、自分なりに発見をしたり、わかったを繰り返してきた。大きくなるにつれ、発見の累積がされて質問することは少なくなっていく。それに反比例するように、アルキメデスほどでないにしても、熟慮に熟慮を重ねて何かを発見するという経験を持つ人は多いだろう。自分なりの「ユーレカ」であり、裸になって街を走ることはないが、天にも昇る気持になる。
このユーレカはおそらく人間が味わうことのできる最も深い快楽であり、その欲求は生理的欲求を圧倒するだろうという専門家の話を聞いたことある。しかしユーレカは常に求め続ける努力がなければ得られないだろう。
男女共同参画基本法が施行されて10年が経過した。国連で女子差別撤廃条約が採択されて30年の節目の年でもある。まだ目指す姿にはなっていないが、この間多くのユーレカがあり、積み上げてきた。この歴史を踏まえ、求め続けていけば、より深いユーレカはやってくるだろう。
浜名湖のほとりで 高部宗夫
質問の数は少なくなるが、質問のレベルは上がってきて、時にはすぐに答えらずにインターネットや辞書で調べることも増えてくる。しかも説明がうまくできなかったり、要領を得なかったりすると時間がかかる。でも理解した時の「わかった」という満足そうな顔を見ると教え甲斐がある。
ギリシャの物理学者アルキメデスは風呂の中で浮力の原理が頭の中に閃いた瞬間「ユーレカ」と叫んで風呂から飛び出し、裸のまま街を走ったという伝説がある。熟慮に熟慮を重ねた末の「ユーレカ」という嬉しさが溢れていたのだろう。「ユーレカ」とはギリシャ語で「発見した、わかった」という意味である。
私たちにも経験はあるだろう。小さい時は親や先生などに何でも質問してきて、自分なりに発見をしたり、わかったを繰り返してきた。大きくなるにつれ、発見の累積がされて質問することは少なくなっていく。それに反比例するように、アルキメデスほどでないにしても、熟慮に熟慮を重ねて何かを発見するという経験を持つ人は多いだろう。自分なりの「ユーレカ」であり、裸になって街を走ることはないが、天にも昇る気持になる。
このユーレカはおそらく人間が味わうことのできる最も深い快楽であり、その欲求は生理的欲求を圧倒するだろうという専門家の話を聞いたことある。しかしユーレカは常に求め続ける努力がなければ得られないだろう。
男女共同参画基本法が施行されて10年が経過した。国連で女子差別撤廃条約が採択されて30年の節目の年でもある。まだ目指す姿にはなっていないが、この間多くのユーレカがあり、積み上げてきた。この歴史を踏まえ、求め続けていけば、より深いユーレカはやってくるだろう。
浜名湖のほとりで 高部宗夫
Posted by あざれあ理事 at
05:22
│Comments(0)
2009年08月17日
地震お見舞い
まずは8月11日の静岡地震のお見舞いを申し上げます。
すごかったですね。揺れ 。
。
皆様におかれましては、被害の状況は如何だったでしょうか。
「あざれあ」でもホール横の大理石の壁が一部崩落したと伺っております。人が集まる時間帯でなくて良かったですね。
東海地震が叫ばれてから耐震構造、家具の固定化、食糧の備蓄等の呼びかけで地震は身近に感じていましたが、この経験で一層の点検が必要に思われました。
この間の台風やゲリラ豪雨による災害を見ますと本当に地球は病んでいると心底思います。
どうなるのでしょうか?この地球!
次世代に付けを回してはいけません。
エコがファションでなく、日常になりますように!
田嶋 清子
すごかったですね。揺れ
 。
。皆様におかれましては、被害の状況は如何だったでしょうか。
「あざれあ」でもホール横の大理石の壁が一部崩落したと伺っております。人が集まる時間帯でなくて良かったですね。
東海地震が叫ばれてから耐震構造、家具の固定化、食糧の備蓄等の呼びかけで地震は身近に感じていましたが、この経験で一層の点検が必要に思われました。
この間の台風やゲリラ豪雨による災害を見ますと本当に地球は病んでいると心底思います。
どうなるのでしょうか?この地球!
次世代に付けを回してはいけません。
エコがファションでなく、日常になりますように!

田嶋 清子
Posted by あざれあ理事 at
12:34
│Comments(0)
2009年08月10日
季節感と「あざれあ」への想い
NPO法人理事2期目で、ブログ初登場 です!
です!
今年の静岡県内の梅雨明けは遅く、やっと蝉の合唱が聞かれる頃となりました。
最近、食育が話題となっていますが、食卓を飾る“野菜や果物”に、季節によって、その味覚を味わうことが少なくなりつつありますが、坪庭に植えたトマト、胡瓜、茄子,ゴーヤ等が実って、夏を味わっています。
男女共同参画センター「あざれあ」の愛称は、全国からの応募によって付けられたもので、私は開館当時の「あざれあ」に勤務し、春の季節には、「アザレア」(ツツジ科)でセンターを飾ることを考え、南側の暖地に「アザレアの苗」を植えてみました。しかし、土壌や気候等の環境が合わず、今では、正面庭に植えた「紅白のツツジ」と4階ロビー北壁に掛けたステンドグラスに描かれた「アザレアの花」を見るだけとなってしまいました。
静岡市内でも、駿府城跡の土手に咲く桜や彼岸花で春や秋を感じますが、あざれあ交流会議は四季折々の自然を彩る花のように、皆さんから愛される館づくりに努めておりますので、是非いつでも皆さんが静岡県男女共同参画センター「あざれあ」に来館し、楽しく活動していただけるようお待ちしております。
理 事 佐 野 牧夫 (富士市 在住)
<あざれあ4階ロビーの「ステンドグラス」とアザレアの解説>


アザレア(Azalea) は、秋~翌春にかけて花を咲かせツツジ科ツツジ属の半耐寒性常緑低木です。 台湾原産のタイワンサツキやツツジがヨーロッパに輸出され、主としてベルギーやオランダなどで改良された園芸品種です。 樹高の大きいものでは、200cmにもなります。
 です!
です!今年の静岡県内の梅雨明けは遅く、やっと蝉の合唱が聞かれる頃となりました。
最近、食育が話題となっていますが、食卓を飾る“野菜や果物”に、季節によって、その味覚を味わうことが少なくなりつつありますが、坪庭に植えたトマト、胡瓜、茄子,ゴーヤ等が実って、夏を味わっています。
男女共同参画センター「あざれあ」の愛称は、全国からの応募によって付けられたもので、私は開館当時の「あざれあ」に勤務し、春の季節には、「アザレア」(ツツジ科)でセンターを飾ることを考え、南側の暖地に「アザレアの苗」を植えてみました。しかし、土壌や気候等の環境が合わず、今では、正面庭に植えた「紅白のツツジ」と4階ロビー北壁に掛けたステンドグラスに描かれた「アザレアの花」を見るだけとなってしまいました。
静岡市内でも、駿府城跡の土手に咲く桜や彼岸花で春や秋を感じますが、あざれあ交流会議は四季折々の自然を彩る花のように、皆さんから愛される館づくりに努めておりますので、是非いつでも皆さんが静岡県男女共同参画センター「あざれあ」に来館し、楽しく活動していただけるようお待ちしております。
理 事 佐 野 牧夫 (富士市 在住)
<あざれあ4階ロビーの「ステンドグラス」とアザレアの解説>


アザレア(Azalea) は、秋~翌春にかけて花を咲かせツツジ科ツツジ属の半耐寒性常緑低木です。 台湾原産のタイワンサツキやツツジがヨーロッパに輸出され、主としてベルギーやオランダなどで改良された園芸品種です。 樹高の大きいものでは、200cmにもなります。
Posted by あざれあ理事 at
01:00
│Comments(0)
2009年08月02日
シズ子さん
大塚です。
佐野洋子さんの2冊のエッセイを読みました。
1冊は「役立たずの日々」実に楽しい、
腹がよじれるようなエッセイでした。
ヨン様にはまってしまった日々のなんとも愉快な話に引きこまれてしまいました。
もう一冊は「シズ子さん」
幼いころ母親のシズ子さんから邪けんに手を振り払われて以来、
「母の手をさわったことがない。
抱きしめられたこともない」と愛されないと思いこんでしまった筆者。
弟夫婦と住んでいたシズ子さんが自分で建てた家から追い出されて、
筆者の家に引き取ることになったこと。
ついにはまだらぼけになったシズ子さんを、
老人ホームに追い出し、
その穴埋めに月30万円の費用を負担、毎日のように見舞に出かける妹に引き比べ、
負担するけれどめったに会いに行くでもない筆者。
ついにはシズ子さんとこの上ない和解にいたるという物語です。
この佐野洋子氏は「100万回生きたねこ」「だってだってのおばあちゃん」の作者でもあります。
彼女は、かって、戦後、大陸から引き揚げてきたあと、静岡の駿府公園の中にあった官舎に住んでいた。
おそらく、父親が学校に職を得てのことだと思われますが、
その話に、嬉しくなってしまいました。
(最近そこに住んでいたという仲間の一人の聞いたばかり)
ただこの父親は若くして亡くなり、
四十幾歳で母一人5人の子どもを大学を卒業させたという、
たのもしいシズ子さんでもあるのですが、母親の一代記をなんともユーモラスに心温まるお話に仕上げているのはさすが……というばかりです。
佐野洋子さんの2冊のエッセイを読みました。
1冊は「役立たずの日々」実に楽しい、
腹がよじれるようなエッセイでした。
ヨン様にはまってしまった日々のなんとも愉快な話に引きこまれてしまいました。
もう一冊は「シズ子さん」
幼いころ母親のシズ子さんから邪けんに手を振り払われて以来、
「母の手をさわったことがない。
抱きしめられたこともない」と愛されないと思いこんでしまった筆者。
弟夫婦と住んでいたシズ子さんが自分で建てた家から追い出されて、
筆者の家に引き取ることになったこと。
ついにはまだらぼけになったシズ子さんを、
老人ホームに追い出し、
その穴埋めに月30万円の費用を負担、毎日のように見舞に出かける妹に引き比べ、
負担するけれどめったに会いに行くでもない筆者。
ついにはシズ子さんとこの上ない和解にいたるという物語です。
この佐野洋子氏は「100万回生きたねこ」「だってだってのおばあちゃん」の作者でもあります。
彼女は、かって、戦後、大陸から引き揚げてきたあと、静岡の駿府公園の中にあった官舎に住んでいた。
おそらく、父親が学校に職を得てのことだと思われますが、
その話に、嬉しくなってしまいました。
(最近そこに住んでいたという仲間の一人の聞いたばかり)
ただこの父親は若くして亡くなり、
四十幾歳で母一人5人の子どもを大学を卒業させたという、
たのもしいシズ子さんでもあるのですが、母親の一代記をなんともユーモラスに心温まるお話に仕上げているのはさすが……というばかりです。
Posted by あざれあ理事 at
09:01
│Comments(0)