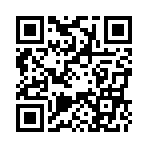2010年01月22日
種が芽吹きました【eカレッジ】

春の訪れを告げるのが、「花粉症」というのはちょっと悲しいですが
 、ここ数日なんだか鼻がムズムズしているあざれあ理事のまつだです。
、ここ数日なんだか鼻がムズムズしているあざれあ理事のまつだです。たびたびの登場にて失礼致します

------------☆
平成に21年度にあざれあ交流会議の自主事業として実施された女性の就労支援講座「eカレッジ(イーカレッジ)」。
再就職を目指す子育て中のママたち対象に全11回の講座を企画し、私はその担当理事として事業全般に携わりました。
さて先日のこと、ある会合で講座の卒業生のおひとりと偶然再会しました。
私はちょうど会議の最中だったし、彼女は仕事中で声をかけることはできませんでしたが、目と目が合って、しっかり言葉のない会話を交わしました。
彼女は、受講生の頃から明るい笑顔のステキなお母さんでした

家族をとても愛していて「ここ数年は、子育てだけに一生懸命でした。」と自己紹介していました。
そんな彼女がステキな笑顔そのままに、社会へ一歩踏み出して生き生きと働いていたのです

ユニフォームも似合っていました。
ほんの一瞬の出来事だったけれど、なんだか・・・胸が・・ジ~ンとしました。
家事と子育て、そして仕事の両立は大変だけれど、これからもがんばってねっ!
あざれあ交流会議は、これからも「働きたい女性」を応援していきます


2010年01月15日
韓国放送公社(KBS)の取材を受けました
交流会議理事のまつだです。
ごあいさつが大変遅くなりましたが、今年もどうぞよろしくお願い致します
私は、地域のIT化支援と女性の社会参加を応援するNPO e-Lunch(イーランチ)を主宰しておりますが、ここ数年は、青少年のインターネット安全利用を促進する活動の講演や講座のご依頼が多くなっております。
そんなe-Lunchに、1月7日、2010年最初の大きな出来事がありました。
韓国の国立放送である韓国放送公社(KBS)の『KBS特集ドキュメンタリー』番組の取材を受けたのです。

ご存じのとおり韓国はネット普及率92%を誇るIT先進国ですが、情報モラルの教育は立ち遅れており、それによる弊害が大きな社会問題になっているそうです。
特に子供たちは、このような危ないインターネット利用環境にさらされていて、情報モラルに対する認識や一抹の責任感も持たずに、無責任ないたずらな書き込みをし、不法ダウンロードによるデジタルコンテンツの著作権侵害は深刻な現状とのことです。
そこで国立放送である韓国放送公社(KBS)はこのような状況が限界に来たと認識し、この問題を直していかなければならないということで、今回の特集ドキュメンタリーを企画するにいたり、企画作業の過程で、e-Lunchのホームページをみつけて下さいました。
さらにe-Lunchに声をかけて下さったきっかけには、単なる「情報モラルを教育する団体」というだけではなく、母親が中心の団体であるe-Lunchが提供する講座や講演に出てくる「親子の絆」という言葉が胸に刺さった、ということでした。
フィルタリングのような技術的な対策だけでは子供は守りきれない、最後に子供を守れるのは、豊かなコミュニケーションによって醸造された親子の絆である、というe-Lunchの主張。
それこそが韓国でも今、必要とされていると感じていらっしゃるようでした。

取材は、インタビューやミーティングの様子が中心でしたが、コーチングスキルを取り入れた演習は特に興味深く、時間を割いて撮影されていました。
ところで取材を担当された洪(コウ)さんは、韓国生まれのアメリカ育ち、現在は日本人の奥様と日本に住んでいらっしゃる国際派です。(もちろん日本語堪能!)
そういった経歴を持ちながら、日本古来の文化に非常に興味を持ち、その良さを言葉の限りを尽くして話して下さいました。
外側から語られる日本の伝統や文化は、我々日本人がもっと誇りを持っていいのかもしれない…と、思わせてくれる嬉しいものでした。
相手を思いやり気持ちを推し量れる国民性、奥ゆかしさのある文化、我慢するという美徳…、洪(コウ)さんから溢れ出る言葉の数々は、今、失われつつある目に見えない日本の財産を、今一度見直させてくれるものでした。
そういった、本来日本人が持っている気質や育ててきた文化を思い出し、それを親子の絆というところに高めつつ情報モラルを子供たちにも伝えることで、子どもたちをネットの事件やトラブルから守れたら本当にすばらしい、素直にそう思いました。
文化の違う韓国で、私たちの活動がどれほど受け入れられるものかはわかりませんが、ひとつの事例として少しでもお役に立てたのなら、こんなに嬉しい事はありません。
放送は1月22日に予定されていますが、編集が終わったら、DVDにして送って下さる、とのことでした。
自分たちの映像にハングル文字の字幕が付く感覚って、どんな感じなんでしょう。
いずれにしてもとても楽しみです。
2010年も幸先のいいスタートを切らせていただきました。
もちろん男女共同参画事業も、がんばります

ごあいさつが大変遅くなりましたが、今年もどうぞよろしくお願い致します

私は、地域のIT化支援と女性の社会参加を応援するNPO e-Lunch(イーランチ)を主宰しておりますが、ここ数年は、青少年のインターネット安全利用を促進する活動の講演や講座のご依頼が多くなっております。
そんなe-Lunchに、1月7日、2010年最初の大きな出来事がありました。
韓国の国立放送である韓国放送公社(KBS)の『KBS特集ドキュメンタリー』番組の取材を受けたのです。

ご存じのとおり韓国はネット普及率92%を誇るIT先進国ですが、情報モラルの教育は立ち遅れており、それによる弊害が大きな社会問題になっているそうです。
特に子供たちは、このような危ないインターネット利用環境にさらされていて、情報モラルに対する認識や一抹の責任感も持たずに、無責任ないたずらな書き込みをし、不法ダウンロードによるデジタルコンテンツの著作権侵害は深刻な現状とのことです。
そこで国立放送である韓国放送公社(KBS)はこのような状況が限界に来たと認識し、この問題を直していかなければならないということで、今回の特集ドキュメンタリーを企画するにいたり、企画作業の過程で、e-Lunchのホームページをみつけて下さいました。
さらにe-Lunchに声をかけて下さったきっかけには、単なる「情報モラルを教育する団体」というだけではなく、母親が中心の団体であるe-Lunchが提供する講座や講演に出てくる「親子の絆」という言葉が胸に刺さった、ということでした。
フィルタリングのような技術的な対策だけでは子供は守りきれない、最後に子供を守れるのは、豊かなコミュニケーションによって醸造された親子の絆である、というe-Lunchの主張。
それこそが韓国でも今、必要とされていると感じていらっしゃるようでした。

取材は、インタビューやミーティングの様子が中心でしたが、コーチングスキルを取り入れた演習は特に興味深く、時間を割いて撮影されていました。
ところで取材を担当された洪(コウ)さんは、韓国生まれのアメリカ育ち、現在は日本人の奥様と日本に住んでいらっしゃる国際派です。(もちろん日本語堪能!)
そういった経歴を持ちながら、日本古来の文化に非常に興味を持ち、その良さを言葉の限りを尽くして話して下さいました。
外側から語られる日本の伝統や文化は、我々日本人がもっと誇りを持っていいのかもしれない…と、思わせてくれる嬉しいものでした。
相手を思いやり気持ちを推し量れる国民性、奥ゆかしさのある文化、我慢するという美徳…、洪(コウ)さんから溢れ出る言葉の数々は、今、失われつつある目に見えない日本の財産を、今一度見直させてくれるものでした。
そういった、本来日本人が持っている気質や育ててきた文化を思い出し、それを親子の絆というところに高めつつ情報モラルを子供たちにも伝えることで、子どもたちをネットの事件やトラブルから守れたら本当にすばらしい、素直にそう思いました。
文化の違う韓国で、私たちの活動がどれほど受け入れられるものかはわかりませんが、ひとつの事例として少しでもお役に立てたのなら、こんなに嬉しい事はありません。
放送は1月22日に予定されていますが、編集が終わったら、DVDにして送って下さる、とのことでした。
自分たちの映像にハングル文字の字幕が付く感覚って、どんな感じなんでしょう。
いずれにしてもとても楽しみです。
2010年も幸先のいいスタートを切らせていただきました。
もちろん男女共同参画事業も、がんばります


2010年01月13日
今年もよろしくお願いします
あけましておめでとうございます。
みなさんは、どのようなお正月をお過ごしでしたか。
我が家は、遠くに離れて住む2人の息子夫婦と孫が3人、暮れからどっと押し寄せて、3泊4日すごして帰りました。
通常は、夫婦2人の生活なのに、合計9人の食事と洗濯には、少々くたびれましたが、一年に一回のことなので、口では、「大変なのよ」と言っても結構嬉しい毎日でした。夫も孫と遊んだり、掃除をしたりと頑張ってくれましたが、何といっても、這い這いして動き回る9ヶ月の男の子、その上の2歳になったばかりのおしゃまな女の子、そして次男の子どもは4歳の幼稚園年少という、元気はつらつそのものの男の子。そんなに広くない、座敷と居間と台所を所狭しと動き回る元気な孫達をみると、老体だとわかっていても一生懸命世話をしてしまい、帰ってからどっと疲れが出てしまったというお正月でした。
さすが、息子達は現代っ子。子どものオムツを換えるのも寝かしつけるのも、上手なものです。それを見た夫は、「俺は子どものオムツをかえたことは、なかったなあ」と、息子がすることなすことに、感心しきりです。最初の頃は、「なぜ、母親がしないのか?」と疑問に思ったそうですが・・・。
さて、例年の初詣は富士宮浅間神社か三島大社に行くのですが、余りの大所帯で、移動が大変ということで、近くの氏神様へ行こうということになりました。歩いて10分ほどの神社へ行きますと、近くの知り合いの方々が、お参りにきておりました。お正月の大人の行動に付き合って、行動を規制されていた反動のように、孫達は、広い境内を走り回り大喜びでした。
大人たちは、神妙に「今年は、景気がよくなりますように」とか、「子ども達が健やかに育ってほしい」、「家族が健康で暮らせるように」と、拝みました。
孫達も、小さな手を合わせて、大人の真似をしていると、近所の方に、「かわいいねえ」と、声をかけられました。
私は、個人的な願いと共に、長年取り組んでいる市民活動の運営がスムーズにいくように、他力を借りるつもりで、お願いをしました。神、仏に願いを頼むということは、お願いしたからどうのということではないのに、自然と頭をたれてしまう動作は、小さい時からの習慣がさせるのでしょうか。
今年も元気でみなさんと共に、「男女共同参画をすすめていく事業」に取り組んでいけたらいいなあと思っています。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

松本玲子
みなさんは、どのようなお正月をお過ごしでしたか。
我が家は、遠くに離れて住む2人の息子夫婦と孫が3人、暮れからどっと押し寄せて、3泊4日すごして帰りました。
通常は、夫婦2人の生活なのに、合計9人の食事と洗濯には、少々くたびれましたが、一年に一回のことなので、口では、「大変なのよ」と言っても結構嬉しい毎日でした。夫も孫と遊んだり、掃除をしたりと頑張ってくれましたが、何といっても、這い這いして動き回る9ヶ月の男の子、その上の2歳になったばかりのおしゃまな女の子、そして次男の子どもは4歳の幼稚園年少という、元気はつらつそのものの男の子。そんなに広くない、座敷と居間と台所を所狭しと動き回る元気な孫達をみると、老体だとわかっていても一生懸命世話をしてしまい、帰ってからどっと疲れが出てしまったというお正月でした。
さすが、息子達は現代っ子。子どものオムツを換えるのも寝かしつけるのも、上手なものです。それを見た夫は、「俺は子どものオムツをかえたことは、なかったなあ」と、息子がすることなすことに、感心しきりです。最初の頃は、「なぜ、母親がしないのか?」と疑問に思ったそうですが・・・。
さて、例年の初詣は富士宮浅間神社か三島大社に行くのですが、余りの大所帯で、移動が大変ということで、近くの氏神様へ行こうということになりました。歩いて10分ほどの神社へ行きますと、近くの知り合いの方々が、お参りにきておりました。お正月の大人の行動に付き合って、行動を規制されていた反動のように、孫達は、広い境内を走り回り大喜びでした。
大人たちは、神妙に「今年は、景気がよくなりますように」とか、「子ども達が健やかに育ってほしい」、「家族が健康で暮らせるように」と、拝みました。
孫達も、小さな手を合わせて、大人の真似をしていると、近所の方に、「かわいいねえ」と、声をかけられました。
私は、個人的な願いと共に、長年取り組んでいる市民活動の運営がスムーズにいくように、他力を借りるつもりで、お願いをしました。神、仏に願いを頼むということは、お願いしたからどうのということではないのに、自然と頭をたれてしまう動作は、小さい時からの習慣がさせるのでしょうか。
今年も元気でみなさんと共に、「男女共同参画をすすめていく事業」に取り組んでいけたらいいなあと思っています。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

松本玲子
タグ :男女共同参画
Posted by あざれあ理事 at
09:17
│Comments(1)
2010年01月12日
地域の見守りをしています!!
地域の見守りをしています!!
長泉町では町内を3小学校区に分け、区長・幼稚園・学校関係者・保護者・交通安全委員・民生委員・補導員などがボランティアで構成員になり、地域の安心・安全のための活動をしています。3地区それぞれ地域にあった活動をしています。
南部地域の活動
1.この地域の犯罪状況を地域の人々に知ってもらうために、地図を作成。公共施設・銀行・スーパーなどに掲示しました。地図の作成には地域の企業の応援を得ました。

2.毎月20日をパトロールの日と決め参加は自由で危険箇所のチェックなどをし、地図に示し、また危険の回避の処置を区・行政に提言しています。

中部地域の活動
拍子木を作り地域の見回りをしています。


・次回は北部地域の活動の紹介をしたいと思います。
・自分たちの地域が安心して住みよい環境になることを心から願っています。そのための活動をしている方、アイディアを教えていただけたらうれしいです。
理事 大川 須津子
長泉町では町内を3小学校区に分け、区長・幼稚園・学校関係者・保護者・交通安全委員・民生委員・補導員などがボランティアで構成員になり、地域の安心・安全のための活動をしています。3地区それぞれ地域にあった活動をしています。
南部地域の活動
1.この地域の犯罪状況を地域の人々に知ってもらうために、地図を作成。公共施設・銀行・スーパーなどに掲示しました。地図の作成には地域の企業の応援を得ました。

2.毎月20日をパトロールの日と決め参加は自由で危険箇所のチェックなどをし、地図に示し、また危険の回避の処置を区・行政に提言しています。

中部地域の活動
拍子木を作り地域の見回りをしています。


・次回は北部地域の活動の紹介をしたいと思います。
・自分たちの地域が安心して住みよい環境になることを心から願っています。そのための活動をしている方、アイディアを教えていただけたらうれしいです。
理事 大川 須津子
Posted by あざれあ理事 at
10:22
│Comments(0)